
サラリーマンがリストラ逆恨みで殺されて、成仏の際に神に反抗した罰で、近代欧州っぽい異世界、WW1前のドイツそっくりな帝国の魔導師の素質持ちの女児に転生。
戦勝と栄達と安穏な後方勤務を夢見つつ、少佐の階級、エース・オブ・エース「白銀」「ラインの悪魔」の二つ名、第二〇三遊撃航空魔導大隊大隊長として、戦場の空を支配する主人公ターニャ・デグレチャフ11歳。12歳になった。

『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
作画の東條チカ先生は、二毛作で『機動戦士ガンダム 水星の魔女』のスピンオフ・コミカライズも同時連載で描き始めましたが、力が分散するどころか、なんか却って『幼女戦記』の筆圧も上がってるようなw
ちなみに、初期巻で度々描かれた「後世の記者が十一番目の女神の謎を追う」後世のエピソードは、同じ作者が描くスピンオフに移行したようです?
aqm.hatenablog.jp
北のレガドニア、西のフランソワ、南の南方大陸ときて、お次は東のルーシー連邦。
帝国(擬ドイツ)東方に国境を接するルーシー連邦、言わずもがなにソビエト連邦をモデルにした国家。
参謀本部の指令でターニャたちがルーシー連邦へ侵入を果たしたまさにその時、ルーシー連邦は帝国に対する宣戦を布告。

『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
魔導士とはいえたった48人で大国・ルーシー連邦の首都・モスコーを蹂躙、敵国首都への浸透作戦、敵国首脳を心胆寒からしめることに成功した第二〇三遊撃航空魔導大隊を待っていたのは、長大な前線の各所から第二〇三遊撃航空魔導大隊への救援要請。
参謀本部から自由遊撃の裁量を任されたターニャの選択は、前線を支える重要補給拠点ながらルーシー連邦軍に包囲され窮地に陥るティゲンホーフ市の救援だった。
ということで、前巻に引き続き、ティゲンホーフ市防衛戦。
今巻はだいたいずーっと戦ってます。
原作者の共産主義嫌いの影響?かルーシー連邦首脳部やその体制がだいぶ無能に描かれますが、首脳部にいる一人の変態が、剛腕と変態的な目的を持って、帝国との戦線に大戦力を投入していく…

『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
前巻までは
あまりに強すぎるその力はそれを怖れる他国をより結託させ、ターニャが最も恐れる「世界大戦」への道を加速させていく…
様子が描かれましたが、今巻では
・西暦を識るターニャの予測を上回るルーシー連邦の攻勢
・航空機・戦車の進化・発展に伴って、相対的に機動力・火力の価値が下がっていく「航空魔導師」という兵科
・遊撃航空魔導大隊の大隊長に納まっているターニャの裁量権限の限界
が語られます。
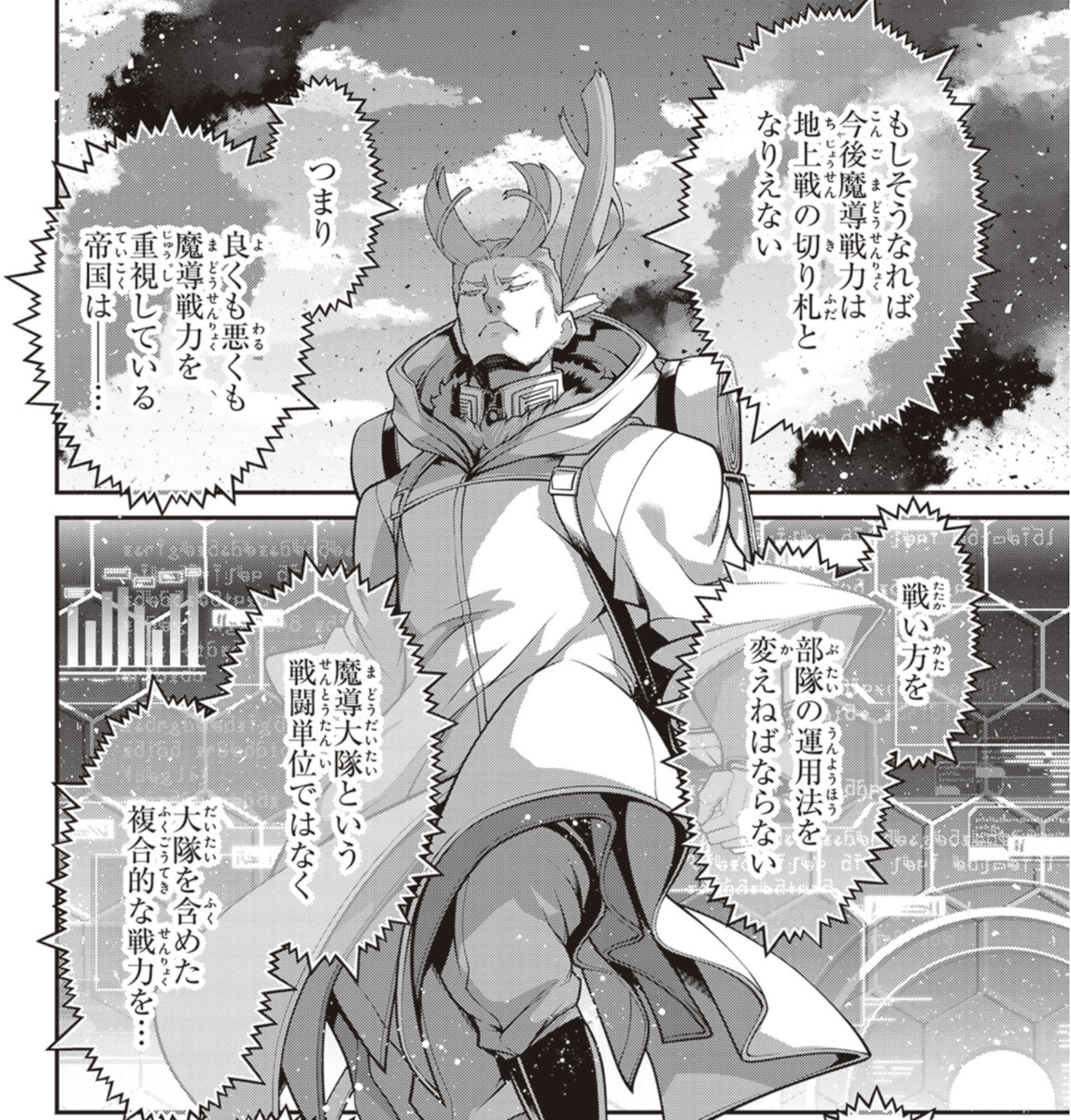
『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
ターニャの能力的にも情勢的にも、大隊長の座は小さすぎる、師団長以上に出世して裁量権持たないと、もう保たない的な。
主人公が航空魔導師であること、その遊撃大隊長であることはこの作品の特徴の一つでしたが、他の兵科も含めて「将軍」になっていくんですかね?
あと、西暦と違う経緯を辿りつつあるのがスリリング。

『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
ちょっとこの先が更に楽しみになってきます。
あとは、
・ルーシー連邦が思想的な理由で航空魔導師部隊を持たないことを、帝国・ターニャたちは知らないんだな
・ターニャの孤児院の幼馴染、どういう役割があるんだろうと思ったら…

『幼女戦記』30巻より(東條チカ/カルロ・ゼン/KADOKAWA)
という感じ。
唐突に査問会に舞台が移って、そっちの行方も気になります。
aqm.hatenablog.jp